ここでは僕自身がやっていることに繋がるまでを時系列にしてお伝えしています。
とても長い文章ですので、興味のある方のみ読み進めてください。
1. 子ども時代:小さな世界と閉ざされた心

「学校は行かなければならない」「休んではいけない」――それが“常識”だった。
しかし、幼い頃からその「当たり前」に強い違和感を抱いていた。
教室に入れば空気は重く、ひそひそ話や押し殺した笑い声が、心の奥底を鋭く刺してくる。
ある時、部活中に2つ上の先輩にいじめられたことで
「ここに自分の居場所はない」
――その現実を、あまりにも早く悟ってしまった。
現実世界は狭く、窮屈で、息苦しい。
だからこそ、自分はゲームの世界に没頭した。

RPGの広大な世界は、正しさや価値観に縛られない。
「なぜこのキャラクターは悪役なのか?」と、物語の裏側にある理由を探ることで、現実では出会えない多様な価値観に触れていた。
2. 不登校という“初めての越境”

中学校1年生の後半から、ついに僕は学校に行かなくなった。(今でいう不登校。昔は登校拒否という名称)
もちろん、最初は罪悪感があった。学校に行かないという選択をするということは、いろんな人に迷惑をかけるということを知っていたからだ。
しかし、なぜか行きたくない。足が動かない。心が危険だと叫んでいる。昇降口がものすごく薄暗くて怖いものでくぐり抜けられない。そういう状態だった。
だが、自分にとっては、初めて「壁の外」に踏み出した瞬間でもあったのだ。
親の心配する顔を見るたびに、胸の奥は締め付けられた。だが、その一方で心は次第に軽くなっていった。
誰もが当然と信じて疑わない場所から、自らの意思で外に出た。
それは、閉ざされた世界の外に広がる、まだ知らない可能性に出会うための第一歩だったのだ。
3. 小さなきっかけが僕を変えた 〜カラオケの奇跡〜
中学の終わり頃には「このままじゃダメだ」と心のどこかで思っていた。
でも、どう変わればいいのか分からず、だったら「高校でリセットをかけよう!」って思い、通信制の高校に入ったことをキッカケに、心を入れ替えて頑張って通いはじめた。
通信制高校で出会った年上の仲間たち。
特に当時30代の兄貴分からはよくお世話になった。
誘われ、初めて訪れたカラオケ。
何度誘われても自分はずっと聞き役だった。マイクを握る勇気などなかった。
しかし、ある日、その兄貴分がこう言った。
「今日は疲れたから、代わりに一曲だけ歌ってよ。」
震える手でマイクを握り、恐る恐る歌い始めた。

「すげぇうまいじゃん!」
その一言が、凍てついた心に小さな火を灯した。
自分は、変われるかもしれない――そう思えた瞬間だった。
その日を境に、週3回カラオケに通うようになった。
人生が、少しずつ色を取り戻し始めたのだった。
4. 「努力は報われる」を初めて知った専門学校時代
「もっと将来を見据えていきたい」。その想いはやがて行動に変わった。
高校の頃にバイト代で溜めたパソコン。ネットゲームに没頭するようになり、ブログも自分で運営するようになっていた。「もっとITを学びたい!」とパソコンの専門学校に進学したのは当然の選択だった。
パソコンの専門学校に進学し、初めて「得意なこと」が認められる経験をした。
テストは常に100点。苦手だったはずの勉強が、初めて面白いと感じられた。
「もっと将来に役立つことを」。そうして挑戦したのが「基本情報技術者」の国家資格だった。
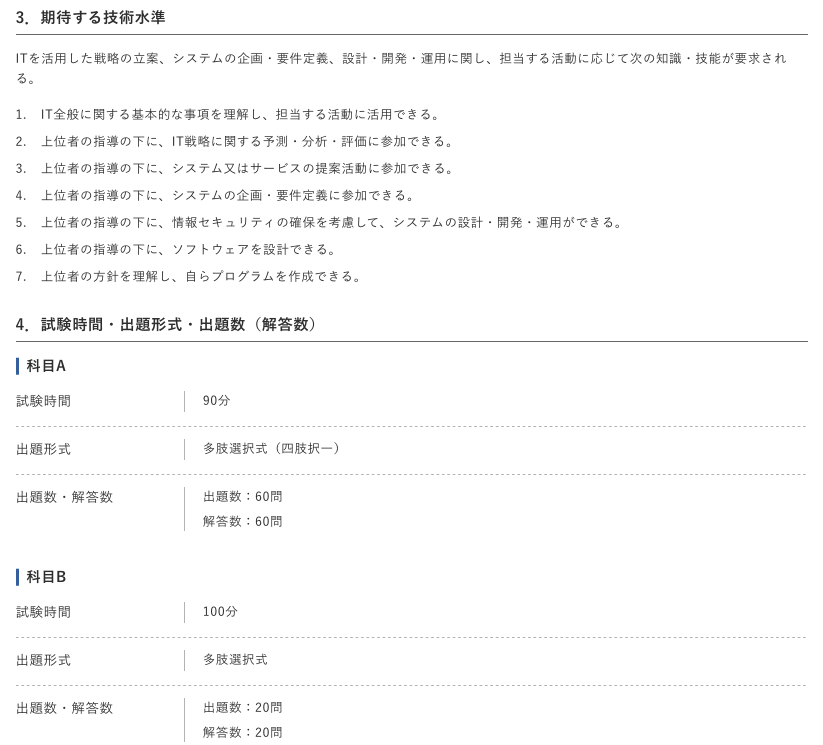
初めて「努力」というものに真正面から向き合った。
朝から晩まで机に向かい、問題集と過去問を何度も繰り返した。
それまで「努力は面倒くさい」と思っていた僕が、コツコツ勉強して、理解できないものが理解できるようになっていくことを感じて初めて「努力の先に光がある」と思えた瞬間だった。
3度目の挑戦で合格を手にした瞬間、心の底から震えた。
「やればできる」――今まで一度も信じられなかった言葉が、ついに自分の中に落ちてきた。
あの日、自分の中でまたひとつ、大きな壁を越えた実感があった。
5. ブラック企業で失った「生きる意味」
しかし、社会に出て待っていたのは、またしても巨大な壁だった。
プログラマーとして入社した会社は、名実ともにブラック企業だった。
暴言、罵倒、長時間労働。人格否定が日常的に繰り返された。
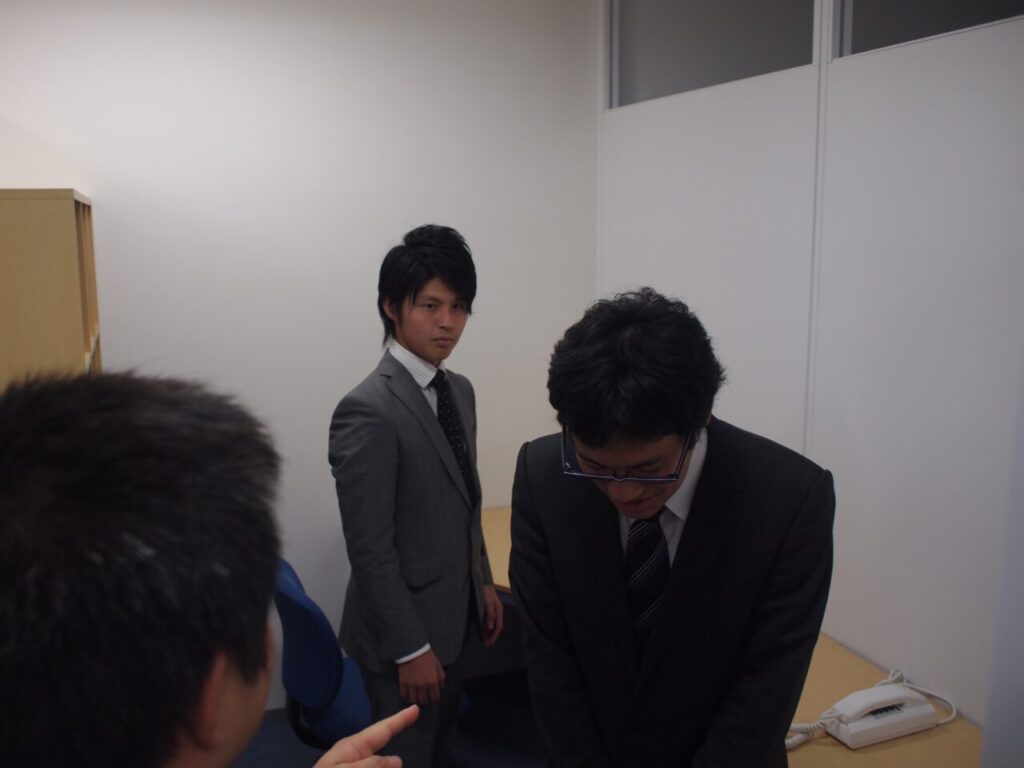
朝6時に起き、帰宅は深夜2時。
電車での通勤に1時間以上、仮眠すら取れないまま翌日を迎えることもしばしばだった。
「これを60歳まで続けるくらいなら、もう……」
そんな危険な考えが、気づけば心の隙間に忍び寄っていた。
親の言葉「石の上にも三年だ」だけを心の支えに、歯を食いしばり働き続けた。
だが、限界はあっけなく訪れた。
心はとうに壊れ、うつ病と診断され、退職をした。
あの時、自分は完全に「価値のない人間」だと信じ込んでいた。
6. 壁の向こうにあった“ありがとう” 〜ICT支援員として〜
壊れてしまった心を抱えながら、自分は「これからどう生きていけばいいのか」と、途方に暮れていた。
そんな中、ハローワークで出会った職員とともに自己分析を繰り返した中で言われた言葉。
「あなたは、誰かを支える仕事が向いているのでは?」

その一言に背中を押され、学校の先生方を支えるICT支援員の仕事に挑戦することになった。
不安だった。
また「お前なんかいらない」と突き放されるのではないかと、何度も心がささやいた。
しかし、現実はまったく違った。
先生たちは、小さなことにも「ありがとう」と笑顔を向けてくれた。
Excelで罫線を引いただけでも、「助かったよ」と心から感謝の言葉を伝えてくれた。
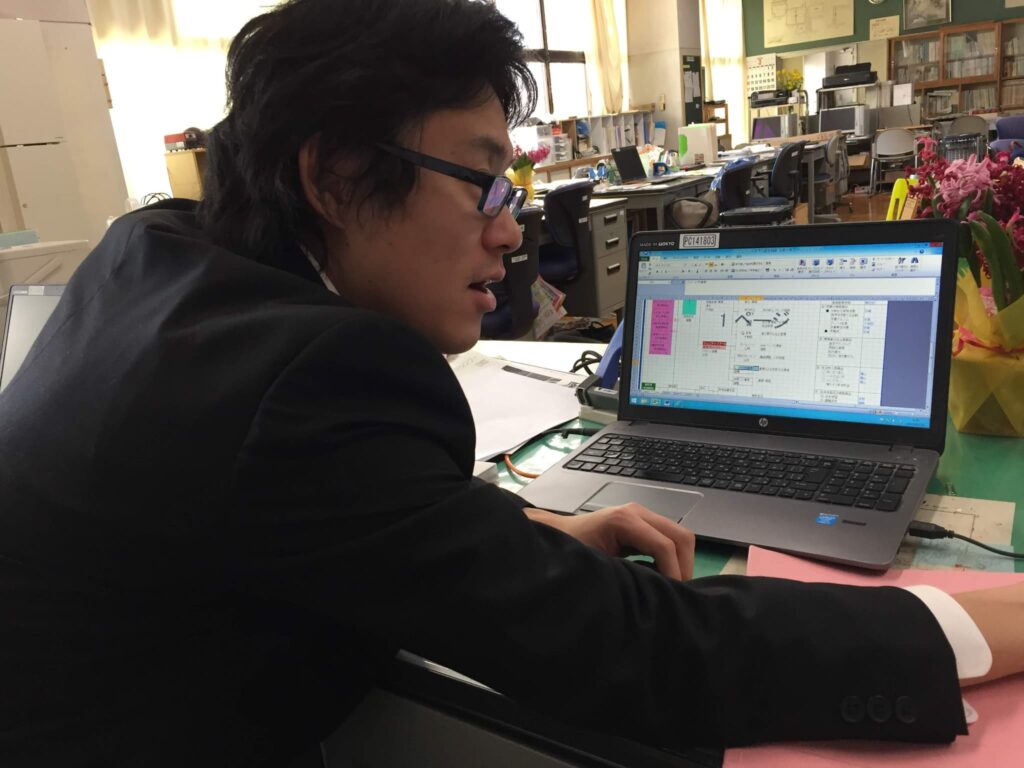
その「ありがとう」が、冷え切っていた心をじんわりと温めてくれた。
「仕事は、こんなにも楽しいものだったのか。」
いつしか、土日が終わるのを待ち望むようになった。
「早く先生たちの役に立ちたい」と心から思い、仕事に向かう足取りが軽くなっていた。
7. 夢を語る勇気と出会ったドリプラの舞台
「もっと多くの先生の役に立ちたい。」
その想いが膨らんでいく中で出会ったのが、「いばらきドリームプラン・プレゼンテーション」だった。
ただ夢を語る場ではない。
100日間、自分の過去と向き合い、「なぜその夢を語るのか?」を徹底的に問い直される場だった。
正直、怖かった。自分の過去も弱さも、すべてをさらけ出すことに大きな抵抗があった。
だが、自分は逃げなかった。
100日間、自分と向き合い続けた。毎日4〜5人と会い、夢を語った。午前は日立、夜はつくばのような普通では考えられない移動距離をほぼ毎日行っていた。しかし、確実に成長していくことを感じた。
そして迎えた本番の日。
スポットライトを浴び、これまでの人生を、心からの言葉で語った。
目の前の観客は、笑い、涙し、共感してくれた。
あの瞬間、自分の存在が誰かの心に届いたことを、はっきりと実感した。
そして、自分は見事に大賞を受賞した。
8. そして今、誰かの心に火を灯すために
振り返れば、人生は「壁」を越える旅だった。
立ち止まり、うずくまり、何度ももう動けないと思った。
それでも、必ず誰かの言葉や出会いが背中を押してくれた。
今、自分は胸を張って言える。
「大人は、最高に面白い。」

この世界は、越えた壁の向こうにこそ、新しい景色が広がっている。
だから今度は、自分が誰かの心に小さな火を灯す番だ。
9. 次世代へ、繋ぐ挑戦
いま、自分は「社会教育士」として、そして一人の“つなぎ手”として、この道を歩んでいる。
地域、学校、家庭。
その間にある見えない壁を取り払い、大人たちがもっと自由に、楽しく、生き生きと暮らす社会を作るために挑戦している。
かつて、「学校に行きたくない」と心を閉ざしていた少年は、
いま「学校と地域の壁をなくしたい」と、未来のために走り続けている。

そして、こう願っている。
「早く大人になりたい!」
子どもたちがそう言ってくれる社会を作ること。
それが、自分の夢であり、使命である。
越えよう、当たり前の壁。
あなたの心にも、小さな火が灯りますように。
そして、いつか一緒に、まだ見ぬ景色を探しに行こう。
ここまで読んでくれたあなたと、きっとどこかで交差する未来があることを信じている。

